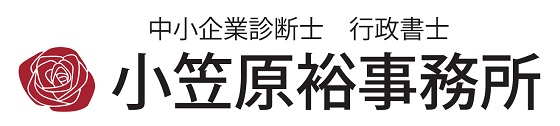相続(11) 遺留分
遺留分とは、相続人が相続できる最低限の相続分を法定したものです。遺言書で、ある相続人の相続分はないと指定されても、遺留分については確保されます。
例えば、法定相続人が兄弟2人のみであったとして、遺言書で兄だけが全財産を相続するよう指定されていても、弟は遺留分については相続することができるのです。
遺留分は、相続順位により異なります。第一順位、即ち子供の遺留分は、法定相続分の2分の1です。第二順位、即ち親の遺留分は、配偶者がいない場合は法定相続分の2分の1、そうでなければ3分の1です。第三順位、即ち兄弟相続の場合は、遺留分はありません。配偶者は常に法定相続分の2分の1です。
遺留分は、相続人から、受益者、即ち法定相続分より多く相続ないしは遺贈を受けたものに対して、減殺請求を行うことで、請求権が形成されます。受益者は、減殺請求をされなければ、遺留分を移す必要はありません。
また、遺留分減殺請求ができるのは、金銭の請求に限ります。これは令和1年7月1日からの規定で、それ以前は不動産などでも遺留分減殺請求の対象となっていました。
遺留分減殺請求は、裁判外でもできますが、遺留分の侵害があったことを知ってから1年以内に行う必要があり、それを超えると請求ができません。
遺言書を作成する際は、できるだけ遺留分を侵害しないように配慮することが、相続の際のトラブルを避けるためにはよいかもしれません。しかし遺留分減殺請求をされなければ、遺留分侵害をした部分も有効ですから、あくまで遺言者の意思で行うのがよいと思われます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 ITプロジェクトマネジメント2024.06.18メキシコでのITプロジェクト支援
ITプロジェクトマネジメント2024.06.18メキシコでのITプロジェクト支援 事務所2024.06.16青龍
事務所2024.06.16青龍 バラの街2024.06.15バラの花がら摘み
バラの街2024.06.15バラの花がら摘み バラの街2024.06.09地元小学校 バラの花がら摘み
バラの街2024.06.09地元小学校 バラの花がら摘み